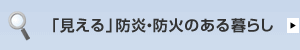弟子が師匠よりも優れた人物になることを「出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ)」と形容する。この「青は藍より出でて藍よりも青し」の言葉は、古代中国の戦国時代の思想家・洵子(じゅんし)の『勧学(かんがく)』に登場する。同じ戦国時代でも日本と違って中国の場合は紀元前で、秦の始皇帝が登場する以前である。ちなみに現存する世界最古の藍染布は古代エジプトで染織された約4000年前の麻布である。このように藍は古代より青の染料として活用されてきた。広く普及した背景には材料入手が容易という以外に、藍の持つ効用が過大に評価されてきた事も大きい。確かに抗菌作用はあるようだが、アメリカの西武開拓時代に登場した青く染めたGパンがガラガラ蛇を退散させるというのは迷信の類(たぐい)だろう。
ところで藍はどのように染めるのだろうか。また染色の工程で咲く「藍の花」とはどのようなものか等々・・・・好奇心が尽きない。ならば百聞は一見にしかずで、疑問を解くため栃木県にある陶芸の町・益子を訪れよう。なぜ益子かというと、ここには「日下田(ひげた)藍染工房」という江戸寛政年間創業の紺屋(藍染屋)が現在も暖簾(のれん)を守っているからである。
しかし陶芸一色の益子に紺屋がある理由は何だろうか。実は益子が陶芸の町として発展するのは人間国宝・故浜田庄司が移り住んで来た昭和以降である。明治の頃までこの一帯は真岡木綿(もおかもめん)で栄え、衣類の80%を藍で染めていたように染織が生活に密着していた。そのはず江戸時代の文化・文政・天保年間には年間38万反生産され、江戸の木綿問屋が扱う60%が真岡木綿であり、染色も淡い水色から濃紺まで約30種類で区別していたという。当然、紺屋も多かったが、明治以降は合成染料の普及で徐々に衰退、現在は同社のみになってしまった。
ここで藍の歴史を概察しよう。藍の色素をインジゴと呼ぶことからも分かるようにルーツは古代インドに遡る。古代ローマで顔料を意味するIndicumもIndia(インド)に由来している。事実、古代インドのサンスクリット語で書かれた文献には製法の記述があるという。もっとも古代中国ではタデアイを栽培していたことから独自に発達したと推測されている。日本でもタデアイを用いることから、染色技術と一緒に大陸から渡来したものであろう。平安時代の中期、967年(康保4年)に施行された延喜式(えんぎしき)には藍染のことが書かれている。江戸時代、都市では藍を供給するための座も結成され、なかでも藍生産地として著名であった京都九条の藍座は藍の売買を独占していたという。
藍には幾つもの種類がある。萩に似たマメ科植物のインド藍は「木藍(きあい)」と呼ばれ、英語名はインジゴ。これ以外にもアメリカ原産の「南蛮駒繋(なんばんこまつなぎ)」、欧州や北海道等の冷涼な地域を好むアブラナ科二年草の「大青(たいせい)」、沖縄の伝統的染物の紅型(びんがた)に使うキツネノマゴ科の「琉球藍」等がある。
古来、日本で藍染に使うのは高さ70㎝ぐらいのタデ科1年草の蓼藍(たであい)。この名前から、「人の好みは様々」を意味する格言「蓼食う虫も好き好き」に登場する雑草の「蓼(たで)」を連想するが、似て非なる物の典型で同じタデ科でも異なる。
蓼藍は東南アジア原産だが、栽培という点では中国が古く、西暦550年に編集された『斉民要術』には製法が記されている。その甲斐あって英語名はChinese Indigoである。日本へは中国から到来した。時期は平安時代の延喜式に登場するので飛鳥時代以前であろう。ひょっとしたら倭の女王・卑弥呼は藍染の倭錦(わきん)を身に着けていたかもしれない。その真偽はともかく日本へ来てから一千数百年の歳月が経過し主要生産地も変遷しているが、江戸時代の中頃以降は徳島県が生産量ナンバー1の座を占めている。
栽培は2月上旬に種を蒔き、春に苗を畑に移す。開花直前の7月中旬に茎から収穫する。葉にはインジカンという成分が含まれ、それが空気に触れると酸化作用によってインジゴという色素に変化し青く発色する仕組みだ。そのためには収穫した葉を刻んで乾燥させ、それを1mほどの高さに積み上げ、数日おきに水を打ち、よくかき混ぜて発酵させなければならない。このようにして約3ヶ月間発酵させ、黒い腐葉土状態になったものを蒅(すくも)と呼ぶ。これを臼(うす)で突き固めたものが藍玉(あいだま)で、2~10%の不溶性のインジゴが含まれている。
次に藍玉を灰汁と一緒に一石五斗(約270リットル)の大きな藍甕(あいがめ)に入れ、木灰・石灰・ふすま等を加えて朝夕かき混ぜると2~3日で褐色の液になり、やがて表面に無数の泡が浮いてくる。これが「藍の華(はな)」で、発酵している証拠でもある。とにかく表現できないぐらいに神秘的な色で誰もが感動するだろう。
最後に「藍の華」の浮かんだ藍甕に布を入れて染色するが、不思議なことに布を引上げた瞬間は茶色っぽい色をしている。しかし心配は杞憂(きゆう)で、瞬く間に藍色へ変化していく。
1856年、英国の化学者パーキンがアニリンからマラリアの特効薬を作ろうとして、結果として出来たのが紫色の染料モーブである。彼はモーブで大儲けをするが、これを合図に合成染料の時代が開始される。インジゴも1883年にドイツのバイヤーによって構造が確認され、ホイマンによって工業化される。藍染が主役の時代は終わったのである。

写真:藍瓶の中で咲いた藍の華